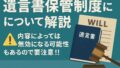東京湾岸エリアの高層マンションに暮らすBさんは、女優として活躍した後、60代まで仕事を続け、約6億円の資産を築きました。老後は投資信託で運用しつつ、夫と娘家族と静かに暮らしていました。しかし80代を迎えるにあたり、娘にできる限りの財産を残したいと考え、相続対策を始めましたが、結果には芳しくありませんでした。そうした 相続対策の失敗 から学んでまいります。
投資信託から不動産へ
知人から「不動産購入は相続税評価額を圧縮できる」と聞いたBさんは、5億円の投資信託を解約し、世田谷区と大田区にそれぞれ2億円ほどの予算で小規模アパートを購入しました。借入をすればより良い物件も選べましたが、「娘に借金を背負わせたくない」という思いから、自己資金のみで購入しました。
相続発生とその後

その数年後、Bさんが亡くなり、アパート2棟と数千万円の現金が娘に相続されました。確かに相続税の課税評価額は下がり、相続税は現金で賄うことができました。しかし、築年数の古いアパートは空室が目立ち、修繕費の備えも必要です。マンションも老朽化が進み、結果として娘が得られる家賃収入は期待ほど多くありませんでした。
表面的な 相続対策の失敗
不動産購入は相続税対策として有効ですが、「評価額が下がる」ことだけを重視すると、かえって遺族に負担を残すことがあります。Bさんが借入を避けた結果、安定収益を生まない物件を残してしまったのです。本来であれば、借入を活用して資産価値の高い物件を選び、家賃収入で返済しつつ将来の資産形成にもつなげる選択肢がありました。
相続対策の失敗 学ぶべきポイント
- 相続税評価の圧縮だけに目を奪われないこと
- 収益性・管理のしやすさを考慮すること
- 借入を「リスク」と捉えるのではなく、レバレッジとして活用する戦略も検討すること
- 金融機関や不動産会社に丸投げせず、専門家のアドバイスを受けること
遺言書作成 もAIの時代
相続対策の第一歩は「資産をどう残すか」を明確にすることです。そのためにも遺言書は欠かせません。
とはいえ、「専門家に依頼すると費用がかかる…」とためらう方もいらっしゃるでしょう。そこで、岡高志行政書士事務所では AIを活用した無料の遺言書自動作成サイト をご提供しています。
その名も 「遺言書AI」。
簡単な入力だけで、あなたに合った遺言書を作成できます。
- 公正証書遺言をご希望の方には、公証役場との調整を有償サポート。
- 複雑なケースでも、行政書士としてのアドバイスをご提供可能。
相続対策を「まだ早い」と思う方も、遺言書の準備は将来の安心につながります。ぜひ 「遺言書AI」 をご活用ください。