近年、相続に関するトラブルを防ぐために「遺言書」を残す方が増えてきました。しかし、せっかく作成した遺言書も、きちんと保管されていなければ効力を発揮できない場合があります。そこで注目されているのが 「法務局による 遺言書保管制度 」 です。この記事では、この制度の内容やメリット、注意点について解説します。
遺言書保管制度 とは?
2020年7月からスタートした制度で、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる仕組みです。従来、自筆証書遺言は自宅などで保管するのが一般的でしたが、紛失・改ざん・発見されないといったリスクがありました。これを解消するために法務局が関与し、安心して遺言を残せるようになったのです。
利用できる遺言の種類は「自筆証書遺言」
この制度で預けられるのは 自筆証書遺言 です。遺言者が全文を自書し、日付と署名押印をして作成する方式です。財産目録についてはパソコンや通帳のコピーを添付することも可能となり、以前より作成しやすくなっていますが、書式などに厳格な決まりがあるので、注意が必要です。
参考:遺言書保管制度(法務省)
遺言書保管制度 のメリット
①安全に保管できる:紛失のリスクがなく安心。
②家庭裁判所の検認が不要:通常、自筆証書遺言は開封時に家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、この制度を利用すれば不要になります。
③相続人がすぐに確認できる:相続開始後、相続人が法務局に照会することで内容を確認できます。
内容が有効かどうかはチェックされないので要注意
さてここからは、この制度のデメリットについても言及します。
内容の有効性まではチェックされない点に要注意!
法務局は形式面のみを確認します。内容の法律的な有効性までは判断しないため、専門家への相談が望ましいです。
有効な遺言書作成のためには、専門家のサポートが重要
遺言書保管制度は、自筆証書遺言をより安心して残すための仕組みです。特に「確実に家族に遺言を伝えたい」「自宅での保管に不安がある」という方におすすめです。ただし、法務局では内容の有効性までは保証していないため、行政書士など専門家のサポートを受けながら作成・利用するのが安心です。
相続トラブルを未然に防ぐために、この制度を上手に活用してみてはいかがでしょうか。
遺言書保管制度 を利用するなら、まずは自筆証書遺言を作成
遺言書保管制度を利用するためには、まずは自筆証書遺言を作成する必要があります。ここからは、自筆証書遺言の作成手順と注意点について解説します。
自筆証書遺言の作成手順
「自分の財産を誰に、どのように遺したいか」を明確に示すために有効なのが遺言書です。「自筆証書遺言」は、紙とペンがあれば作成でき、費用もほとんどかからないため多くの方に利用されています。
1. 用意するもの
- 白い紙(形式に決まりはありませんが、長期保存に耐えるものがおすすめ)
- 黒のボールペンなど修正できない筆記具
- 実印(認印でも有効ですが、実印が望ましい)
2. 作成のルール
自筆証書遺言には法律で定められた厳格な要件があります。
①全文を自分で手書きすること(財産目録はパソコンやコピーでも可)
②日付を明記すること(「令和〇年〇月〇日」と特定できる日付)
③署名と押印をすること
この3点を満たさないと、遺言が無効になる可能性があります。特に「日付の記載ミス」や「財産の特定があいまい」などはトラブルになりやすいため注意が必要です。
3. 書き方の流れ
タイトルを明記:「遺言書」などと記載
本文を書く:誰に何を相続させるかを具体的に書く
日付を記入:「令和〇年〇月〇日」など正確な日付を書く
署名と押印:本人が自署し、印鑑を押す
封印は任意:封をする場合は、相続人が勝手に開けられないよう注意が必要
行政書士にサポートを依頼すると安心
自筆証書遺言は手軽に作れる反面、無効になる危険性が高いという弱点があります。法律的に有効かどうかは自分で判断しづらく、結果的に「せっかく書いたのに使えなかった」という事態も少なくありません。
そのため、専門家である行政書士に相談し、
✅書き方のチェック
✅財産の特定方法
✅相続人間のトラブル予防の工夫
などのアドバイスを受けながら作成すると安心です。
ただ、「専門家に依頼するとなると、費用もかかるし…」と躊躇してしまうこともあるでしょう。
そこでオススメしたいのが、岡高志行政書士事務所が運営する 遺言書 自動作成サイト 「遺言書AI」です。当サイトは、おかげさまで2,500件以上のご利用いただいております。
自筆証書遺言は、誰でも簡単に作れる反面、少しの記載ミスで効力を失ってしまう危険があります。正しく作成し、大切な想いを確実に伝えるためにも、「遺言書AI」をぜひご活用ください。
自筆証書遺言が無効になってしまった実例を紹介
「せっかく遺言書を残したのに、無効になってしまった」──そんな残念なケースは少なくありません。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、法律で定められたルールを守らなければ効力を失ってしまうのです。ここからは、実際に起こった「無効になった事例」を紹介しながら、有効な遺言を作成するためのポイントを解説します。
実例1:日付の記載が不十分だったケース
ある方は遺言書に「令和3年4月吉日」と記載しました。一見問題なさそうに思えますが、法律上「日付が特定できること」が必須条件です。「吉日」では具体的な日を特定できないため、この遺言書は無効とされてしまいました。
実例2:財産の特定があいまいだったケース
「長男に預金をすべて相続させる」とだけ書かれた遺言。実際には複数の銀行口座がありましたが、銀行名や支店、口座番号が書かれていなかったため、どの財産を指しているのか不明確でした。その結果、相続人同士で解釈が分かれ、トラブルになってしまいました。
実例3:署名や押印がなかったケース
高齢の方が手書きで本文を残していましたが、署名や押印をしていませんでした。遺言の最後に自分の名前と印鑑を押すことは必須条件です。それが欠けていたため、裁判所は「遺言としては無効」と判断しました。
実例4:本人が書いたものではなかったケース
体調が悪くなった高齢者のために、家族が代筆したケースです。本人の意思であったことは間違いありませんが、自筆証書遺言は「全文を本人が自書する」ことが条件です。代筆された遺言は無効になり、結局相続人間で揉めてしまいました。
有効な遺言書を作成するためにオススメ「遺言書AI」
このように、自筆証書遺言はちょっとした不備で簡単に無効となってしまいます。法律上のルールは非常に厳格で、「家族のために残した大切な遺言」が使えなくなるリスクが常にあるのです。
そこでおすすめなのが、行政書士にサポートを依頼することです。行政書士に相談すれば、
- 記載方法のチェック
- 財産の特定方法のアドバイス
- トラブルを避ける工夫の提案
といった専門的な支援を受けられます。
自筆証書遺言は費用をかけずに作成できますが、少しのミスで無効となり、かえって家族に迷惑をかけてしまう危険があります。安心して想いを遺すためには、専門家の知識を借りて正しい遺言を作成することが大切です。
「大切な家族に、自分の想いを確実に伝えたい」と考える方は、ぜひ行政書士に相談しながら遺言を準備してみてはいかがでしょうか。
とはいえ、「専門家に相談するには費用もかかるし…」「差し迫って必要なわけではないし…」と感じている方も少なくありません。
そんな方たちにおすすめなのが、AIを活用した遺言書作成の自動作成サイト
画面の見やすさにこだわり、操作も簡単なWEBサイトです。行政書士として高齢者の相談に乗ってきたノウハウが活きています。
長年にわたって、様々なケースの遺言や相続のご相談に携わってきた岡高志行政書士事務所が運営する当サイトは、簡単な入力で遺言書の下書きを作成できます。
あとは、紙とペンを用意して、ご自身で手書きすれば遺言書が完成します。
「いつか」ではなく「今」。元気なうちに遺言書を準備するメリット
「自分はまだ元気だし、財産もそれほど多くないから必要ない」
「遺言書なんて書いたら死を意識してしまいそうで気が重い」
このように考えて、遺言書の作成を後回しにしてしまう方は少なくありません。しかし突然の病気や事故、認知症などで判断能力を失ってしまうと、もう遺言書を書くことはできません。その結果、残された家族が相続手続きで揉めてしまうケースも増えているのです。
今すぐ準備することのメリット
① 家族のトラブルを防ぐ
遺言書がないと、相続は法律に基づいて「法定相続分」で分けることになります。財産が不動産中心で分けにくい場合や、介護を担った子どもとそうでない子どもの間で不満が生じることも。遺言書を残すことで、誰に何を相続させるかを明確にでき、争いを未然に防げます。
② 自分の意思を伝えられる
例えば「自宅は妻に残したい」「事業を継いでいる長男に会社の株を相続させたい」「散骨を希望する」など、相続や葬儀の希望は人それぞれです。遺言書があれば、亡くなった後も自分の思いを形にできます。
③ 財産の整理ができる
遺言書を作る過程で、自分の財産を改めて確認することになります。預貯金、不動産、生命保険、借入金などを整理できるため、老後の生活設計や相続税対策にも役立ちます。
④ 何度でも書き直せる
「今作っても、後で状況が変わったらどうしよう」と不安になる方もいます。しかし遺言書は、何度でも書き直し可能です。だからこそ、とりあえず今の気持ちを形にしておくことが大切なのです。
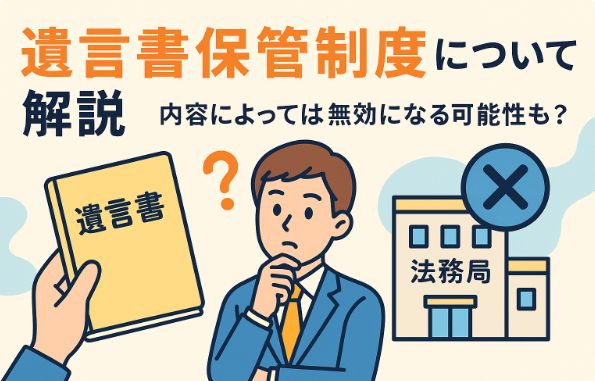
遺言書作成 もAIの時代
人生100年時代の未来の安心のためにも、遺言書作成は必須事項です。それでも、法律専門家に相談するのは料金がかかると二の足を踏む方もいらっしゃるかもしれません。DX(デジタルトランスフォーメーション)を標榜する岡高志行政書士事務所では、AIを活用した遺言書作成の自動作成サイトを運営しております。その名も
「遺言書AI」を利用すれば、簡単な入力で遺言書を作成できます。
人生100年時代、遺言書の作成は、より良く生きるための必須事項ともいえます。そのため、社会貢献の一環として、お客様の利用は無料としております。
公正証書をご希望の方には、公証役場と調整する部分だけを有償サービスで提供しております。
複雑なケースや、公正証書遺言を希望される方には、専門家からのアドバイスも可能です。ぜひ活用してみてください。
画面の見やすさにこだわり、操作も簡単なWEBサイトです。行政書士として高齢者の相談に乗ってきたノウハウが活きています。 ぜひお試しください。



