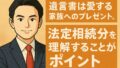人生の最期を見据えて遺言書を作成する方が増えてきましたが、「 遺言執行者 」という言葉にあまり馴染みのない方も多いのではないでしょうか?
皆さん、ご自身の遺言がきちんと実行されたかどうかを見届けることはできません。そこで、ご自身に代わって遺言の内容を執行するのが遺言執行者の役割です。
今回は、遺言書の中で重要な存在である「 遺言執行者 」について、わかりやすく解説していきます。ぜひ参考にしてください。
遺言執行者 とは?
遺言執行者とは、文字通り「遺言を執行する人」のこと。つまり、遺言書に書かれている内容を実際に実行に移す役割を担う人です。
たとえば、遺言に「長男に不動産を相続させる」「〇〇団体に寄付する」などの内容が書かれていれば、それをきちんと実行するのが遺言執行者の仕事になります。

遺言執行者 必要な理由
遺言書があっても、ただそこに書いてあるだけでは効力が十分とは言えません。相続人の間でトラブルになったり、手続きが進まなかったりすることも起こり得ます。
そのような場合でも、遺言執行者が選任されていると、法律に基づいてスムーズに手続きを進めることができるのです。
遺言執行者 主な役割
遺言執行者の権利義務については、以下のように定められています。
- 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
- 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
具体的には、以下のような業務が挙げられます。
- 遺言書の検認や開封手続き
- 財産の調査と整理
- 相続人への財産の引き渡し
- 不動産の名義変更
- 銀行口座の解約・分配
- 債務の支払い
- 遺贈(寄付など)の実行
特に、不動産の名義変更や銀行の手続きなどは、専門知識が必要な場面も多くあります。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
民法 第1012条
遺言執行者 は誰がなれる?
遺言執行者には、基本的に誰でもなることができます。相続人の中から選ばれることもあれば、行政書士などの専門家に依頼するケースも多いです。
また、遺言書の中で「○○を遺言執行者に指定する」と明記することもできます。
遺言執行者を専門家に依頼するメリット
遺言の内容が複雑な場合や、相続人同士の関係に不安がある場合は、行政書士などの専門家を遺言執行者に指定するのがおすすめです。
中立の立場で法的に適切な手続きを進めてくれるため、トラブル防止にもなります。
遺言執行者は、故人の意思を正しく実現するために欠かせない存在です。
遺言書を作成する際には、「この人に任せたい」と思える信頼できる人物や専門家を遺言執行者として指定しておくことで、相続手続きを円滑に進めることができます。
将来のためにも、少しずつ準備を始めてみてはいかがでしょうか?
「遺言執行者を指定しておいて良かった」という方たちのエピソード
「遺言書を作るのはまだ早いかな…」
「遺言執行者って本当に必要なの?」
そう思っている方も多いかもしれません。ですが実際には、遺言執行者を指定しておくことが、家族にとって大きな安心につながったというケースがたくさんあります。
ここでは、そんな「遺言執行者を指定しておいて良かった」と感じた方たちの実例をご紹介します。
エピソード①:兄弟げんかを防げた
登場人物:Aさん(40代・会社員)/父の遺言書により長男が執行者に指定されたケース
「父は生前から『お前たち兄弟は仲が良いけど、財産が絡むと揉めることもあるから』と言って、きちんと遺言書を残してくれていました。
その中で、兄が遺言執行者に指定されていて、相続財産の分け方も具体的に記されていました。
手続きは兄が責任を持って行ってくれたので、他の兄弟は感情的にならずに済み、本当に助かりました。」
家族間のトラブルを未然に防ぐためにも、遺言執行者の存在は大きな意味を持ちます。
エピソード②:専門家に頼んだことでスムーズに相続できた
登場人物:Bさん(60代・主婦)/遺言執行者として行政書士が指定されていたケース
「主人が亡くなったとき、私は何をどうすればいいか全然分かりませんでした。
でも遺言書の中で行政書士の先生が遺言執行者として指定されていたので、その先生が全部リードしてくれて、本当に心強かったです。
銀行や不動産の手続きもスムーズに済みましたし、感情的な場面で専門家が間に入ってくれたのもありがたかったです。」
相続手続きは意外と煩雑。専門家を遺言執行者にしておくことで、家族の負担が大きく軽減されます。
エピソード③:事業承継もスムーズに進んだ
登場人物:Cさん(50代・自営業)/父が遺言執行者に行政書士を指定していたケース
「父が営んでいた家業を、私が継ぐことになっていました。でも他の兄弟も関わっていたので、正直少し不安でした。
父の遺言には、行政書士が遺言執行者として記されていて、事業資産の分配や契約の整理もすべてお任せできたんです。
そのおかげで、遺族の間で揉めることなく、スムーズに承継できました。」
遺言執行者の選び方次第で、事業承継や資産整理の「安心感」はまったく変わってきます。
エピソード④:遺贈がしっかり実現できた
登場人物:Dさん(30代・看護師)/故人がNPO法人に遺贈を希望していたケース
「祖母は生前、ずっと支援していた動物保護団体に寄付をしたいと話していました。
その意志を遺言書に残し、遺言執行者として行政書士の方を指定していたので、きちんと遺贈が実現されました。
本人の思いが形になったこと、家族としても本当に良かったと思っています。」
遺言執行者がいなければ、遺贈の実行が難しい場合もあります。しっかりとした意思表示と、それを形にする仕組みが大切です。
今回ご紹介したエピソードのように、遺言執行者がいたことで「スムーズに手続きが進んだ」「家族間のトラブルを防げた」といったメリットがあります。
遺言書を作るときは、ぜひ遺言執行者の指定も検討してみてください。
遺言執行者 は「安心」のカギ
〜あなたの“想い”を、きちんと届けるために〜
人生の終わりを意識するとき、「自分がいなくなったあと、大切な人たちは大丈夫だろうか?」という気持ちが浮かんでくるのではないでしょうか。
そんなときに、心強い存在となるのが 「遺言執行者」 です。
人生の幕を閉じたあと、自分では何もできません。
どれだけ思いやりを込めて遺言を書いても、それを実行してくれる人がいなければ意味がないのです。
遺言執行者を指定しておくと、こんなメリットがあります
- 遺言の内容が確実に実現される
- 相続人同士のトラブルを防げる
- 手続きがスムーズに進む
- 家族に精神的・時間的な負担をかけない
つまり、遺言執行者とは、ご自身の意思を正確に実行するための「橋渡し役」なのです。
遺言執行者は、法律上は誰でもなれますが、専門家に依頼するほうが安心です。
【行政書士に依頼するメリット】
- 書類の作成や法的な手続きも安心
- 感情が入りにくく、公正・中立な対応ができる
- 相続人同士が揉めたときの調整役にもなれる
実際に遺言執行者の存在が「残された家族の支え」になったという声は少なくありません。
人生の終わりをどう迎えるかは、誰にとっても大切なテーマです。
その中で、「遺言書」と「遺言執行者」は、自分の想いを未来に届けるための、とても大切な準備のひとつ。
あなた自身が納得して旅立ち、ご家族も安心して日々を送れるように――
遺言書の作成と、遺言執行者の指定という選択を、ぜひ前向きに考えてみてください。
未来の安心につながる遺言書作成
~“その日”が来る前に、できること~
「遺言書って、年配の人が作るもの」「まだ自分には関係ない」
そんなふうに思っていませんか?
でも実は、遺言書は“今”を生きる私たちが、未来の大切な人のためにできる優しい準備なのです。
遺言書=「最後のラブレター」
遺言書は単なる財産分配のための書類ではありません。
あなたの大切な想いを、未来に届ける人生のメッセージです。
- 子どもたちへの感謝
- 配偶者へのねぎらい
- お世話になった人への贈り物
- 支援したい団体への遺贈
法的な効力を持つと同時に、遺された人の心に届く“最後のラブレター”になることもあるのです。
遺言書があることで守れる「安心」
遺言書を作成しておくことで、次のような安心が生まれます。
1. 相続トラブルを未然に防げる
相続人同士で「言った・言わない」「誰がどれだけ相続するか」で揉めるケースは少なくありません。
明確な遺言があるだけで、多くの争いを防ぐことができます。
2. 手続きがスムーズに進む
遺言書により、手続きに必要な時間や手間が大幅に軽減されます。
とくに遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きがより円滑になります。
3. 家族の精神的負担を減らせる
大切な人を失った悲しみの中で、複雑な手続きを進めるのはとても大変。
遺言書があると、残された家族の不安や混乱を和らげることができます。
どんな人が遺言書を作るべき?
「財産が多い人だけが作るもの」と思われがちですが、そんなことはありません。
✅ 子どもが複数いる方
✅ 再婚・事実婚・内縁関係の方
✅ 相続人がいない方
✅ 自分の死後、特定の人や団体に寄付したい方
✅ 事業や不動産を持っている方
これらにひとつでも当てはまる場合は、早めの遺言書作成がおすすめです。
自筆?公正証書?どちらがいい?
遺言書には主に2つの種類があります。
● 自筆証書遺言
自分で書く遺言書。手軽ですが、形式ミスによる無効リスクも。
● 公正証書遺言
公証役場で作成する遺言書。確実で安全、そして保管も安心。
確実に実行されたい方には公正証書遺言+遺言執行者の指定がおすすめです。
遺言書作成は「今」だからこそ意味がある
遺言書は、元気なうちに作るからこそ意味があるものです。
「まだ早い」と思っていた方が、実際に書き始めてみると「心が軽くなった」「やるべきことが明確になった」と口をそろえます。
それはきっと、
「大切な人のために、ちゃんと準備できた」という安心が生まれるから。
自分が旅立ったあとに、家族が困らないように。
そして、自分の思いがまっすぐ届くように。
遺言書は、未来の安心をつくる“思いやりのカタチ”です。
今だからこそ、考えてみませんか?
岡高志行政書士事務所では、AIを活用した遺言書作成の自動作成サイトを運営しております。「遺言書AI」を利用すれば、簡単な入力で遺言書を作成できます。
遺言書AIは、ガイダンスに沿って相続人・資産情報などを入力することで、遺言書が無料で作成できるWEBサイトです。 正式な遺言書は 自筆証書遺言 としてご自身で手書きする。もしくは 公正証書遺言 として公証人に作成していただくこととなります。
参考:日本公証人連合会
遺言書作成 もAIの時代
遺言書作成の重要性につきご理解いただけましたでしょうか。
それでも、法律専門家に相談するのは料金がかかると二の足を踏む方もいらっしゃるかもしれません。DX(デジタルトランスフォーメーション)を標榜する岡高志行政書士事務所では、AIを活用した遺言書作成の自動作成サイトを運営しております。その名も
「遺言書AI」を利用すれば、簡単な入力で遺言書を作成できます。
人生100年時代、遺言書の作成は、より良く生きるための必須事項ともいえます。そのため、社会貢献の一環として、お客様の利用は無料としております。
公正証書をご希望の方には、公証役場と調整する部分だけを有償サービスで提供しております。
複雑なケースや、公正証書遺言を希望される方には、専門家からのアドバイスも可能です。ぜひ活用してみてください。
画面の見やすさにこだわり、操作も簡単なWEBサイトです。行政書士として高齢者の相談に乗ってきたノウハウが活きています。 ぜひお試しください。