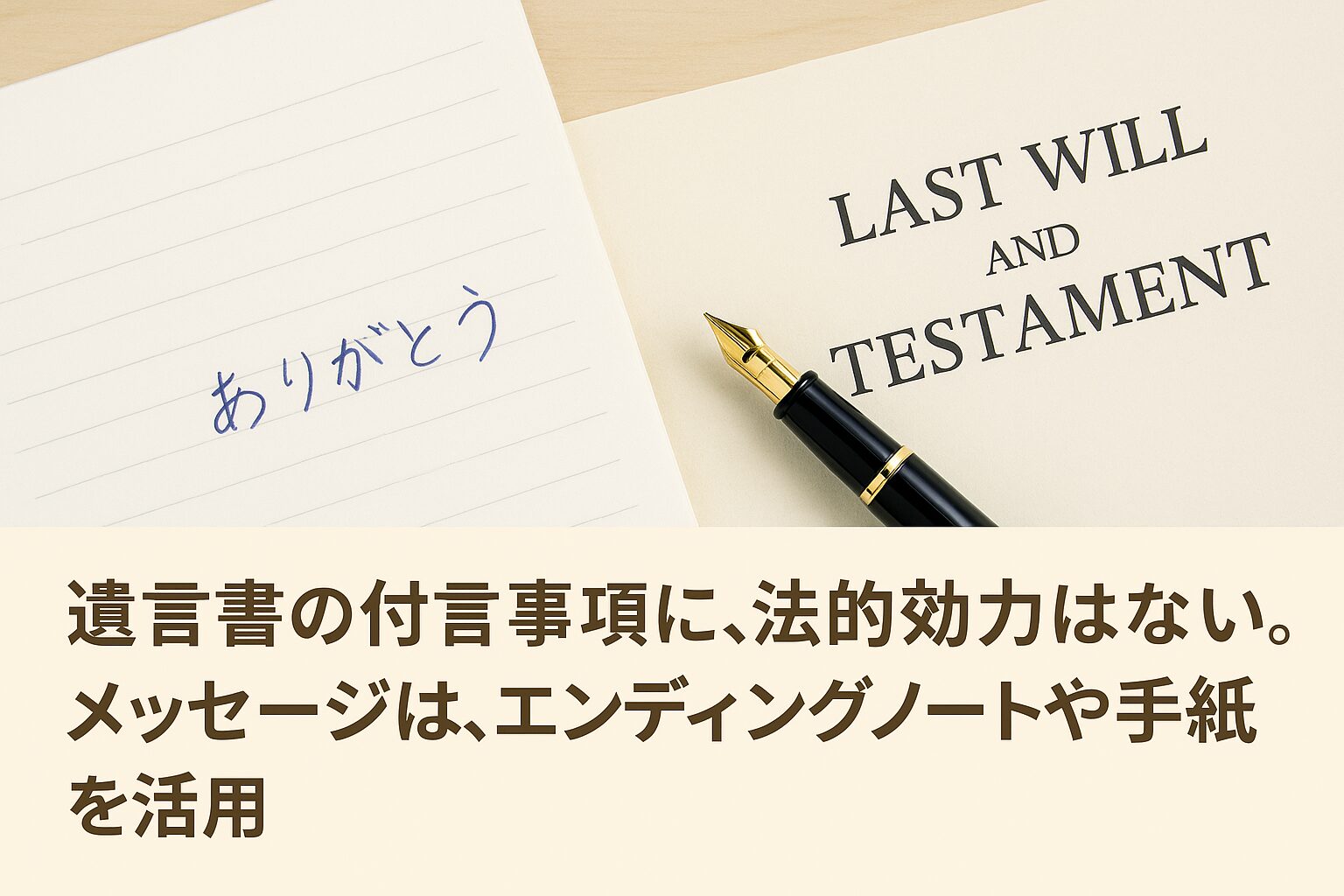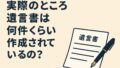遺言書は、亡くなった後に自分の意思を伝える大切な手段です。しかし、「何でも遺言で決められる」というわけではありません。日本の法律では、遺言でできる内容は大きく分けて「相続」「身分」「財産処分」に関することに限られます。今回は、それぞれの項目について分かりやすく解説した上で、 付言事項 についてもご紹介していきます。
参考:日本公証人連合会
遺言で残せる意思表示
相続に関する内容
遺言書で最もよく知られているのが「相続」に関する指示です。具体的には以下のような内容が含まれます。
遺産の分け方(遺産分割方法の指定)
例:長男には自宅を、次男には預貯金を…など具体的に指示できます。
相続人の廃除・廃除の取消
著しい非行があった相続人に対し、相続権を取り消すことができます。
遺贈(遺産を相続人以外に与えること)
友人や団体、介護してくれた人などに遺産を譲ることも可能です。
身分に関する内容
「身分」とは主に家族に関わる法律関係のことを指します。遺言では以下のような身分事項を定められます。
認知
婚外子など、法律上の親子関係を認めることができます。
未成年後見人の指定
被相続人に未成年の子がいる場合、その後見人を指名しておくことができます。
財産処分に関する内容
遺言では、自分の財産の使い道や管理方法についても指定できます。
信託の設定
遺言で信託を設定し、信頼できる人に財産の管理・運用を任せることができます。
遺言執行者の指定
遺言の内容を実行する人(遺言執行者)を選ぶことで、スムーズな手続きを期待できます。
注意点:法定相続人の「遺留分」も考慮を
遺言は自由に書けるものですが、すべてが思い通りに実行されるとは限りません。たとえば、配偶者や子には「遺留分」と呼ばれる最低限の相続分が保障されています。これを侵害すると、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
上記のように、遺言で定められるのは「相続」「身分」「財産処分」の三つが中心です。逆に、これ以外のこと、たとえば日常生活のルールや感情的な願い(「○○とは絶対に付き合うな」など)は、法的効力は持ちません。
遺言書は、法的に有効な形式で財産の分け方などを指定する文書ですが、「付言事項(ふげんじこう)」という、法的効力はないけれど重要な役割を果たす記述があります。ここからは、「付言事項」について解説します。
遺言書の 付言事項 とは?
付言事項とは、遺言書の中に記される、法律上の効力は持たないけれど、遺言者の思いを伝えるための自由記述部分です。法定相続分の指定や遺産分割のような“効力のある内容”とは別に、家族や関係者に向けた気持ちや事情説明を記すことができます。
付言事項に書ける主な内容
遺産の分け方の理由
例:「長男に自宅を相続させるのは、同居して介護をしてくれたからです」
家族への感謝の言葉や励まし
例:「これまで支えてくれてありがとう。皆が仲良く暮らしていってくれることを願っています」
相続トラブル防止のための配慮
例:「公平に分けたつもりです。どうか遺言の通りに受け取ってください」
供養や遺品に関する希望
例:「仏壇は長女に引き継いでほしい」「形見は自由に分けてください」
付言事項は、自由に書いてよい部分なので形式的な制約はありません。
トラブルに発展することも⁉ 付言事項 には要注意
遺言書に「付言事項」として、家族への感謝や遺産分割の理由などを書く人もいますが、その書き方や内容によってはかえってトラブルの火種になることもあります。
ここでは、実際に起こった「付言事項が原因で相続トラブルに発展したケース」を紹介し、注意すべきポイントを解説します。
ケース1:特定の子だけを褒めた結果、他の相続人が反発
概要
遺言書では、長男に自宅と預貯金の大部分を相続させる旨が記載されていました。付言事項にはこう記されていました。
「長男は私の介護を一番よくやってくれた。家族の中で最も信頼できる存在です。これからも家を守ってほしい」
問題点
この言葉に対し、他の子どもたちは「自分たちは評価されていない」「見下された」と感じ、感情的に反発。
法的には問題のない遺言だったにもかかわらず、感情的な対立から遺留分侵害額請求がなされ、調停に発展しました。
ケース2:遺産の不公平感を正当化しようとしたが逆効果に
概要
父親が遺言書の付言事項で次のように記載していました。
「長女には学費や結婚資金で多く援助したので、相続分は少なくしました」
問題点
長女は当時の援助について「生活が苦しかった中での必要最低限の支援だった」と認識しており、「援助を受けたから相続を減らされるのは納得できない」と強く反発。
この説明がかえって長女の怒りをあおり、家族間の関係が悪化しました。
このように、遺言書の付言事項は、意図しない受け取り方をされると、感謝の言葉が逆に火種になることもあるのです。
「トラブル防止」のつもりが「争族」の引き金になってしまうこともあるのです。
残したい想い、伝えたいメッセージがある場合は、エンディングノートや、家族へのお手紙として記すことをおすすめしています。
遺された家族へのメッセージ文例を紹介
エンディングノートやお手紙は、法的効力はないものの、遺族の心に深く残る、大切なメッセージです。
ここでは、実際に使えるメッセージの文例を目的別にご紹介します。
家族への感謝を伝える文例
妻○○へ、長い間連れ添ってくれてありがとう。あなたのおかげで私は安心して人生を歩むことができました。
子どもたちへ、それぞれの道で頑張っている姿を誇りに思います。これからも仲良く、支え合って生きていってください。
遺産分割の理由を説明する文例
長男○○には、自宅を相続させることにしました。これまで家業を支え、私の介護も担ってくれたことに感謝しています。
他の子どもたちにも感謝の気持ちは変わりません。皆が納得のうえで私の遺言を受け入れてくれることを願っています。
仲の良い家族関係を望む文例
遺産の分け方については、私なりに公平になるよう考えました。
どうかこのことで争うことなく、これまで通り、兄弟姉妹で助け合っていってください。
みんなの幸せを、心から願っています。
お世話になった人へのメッセージ文例
介護をしてくださった○○さんには心から感謝しています。おかげで、心身ともに充実した晩年を過ごすことができました。
本当にありがとうございました。
宗教的・精神的メッセージを含めたい場合の文例
私の人生は多くの出会いに恵まれ、感謝の日々でした。
どうか私の死を悲しむよりも、命のバトンを受け継いでいくことを大切にしてください。
仏前での供養は特に希望しません。皆さんの心の中に、私がいればそれで十分です。

遺言書作成 もAIの時代
人生100年時代の未来の安心のためにも、遺言書作成は必須事項です。それでも、法律専門家に相談するのは料金がかかると二の足を踏む方もいらっしゃるかもしれません。DX(デジタルトランスフォーメーション)を標榜する岡高志行政書士事務所では、AIを活用した遺言書作成の自動作成サイトを運営しております。その名も
「遺言書AI」を利用すれば、簡単な入力で遺言書を作成できます。
人生100年時代、遺言書の作成は、より良く生きるための必須事項ともいえます。そのため、社会貢献の一環として、お客様の利用は無料としております。
公正証書をご希望の方には、公証役場と調整する部分だけを有償サービスで提供しております。
複雑なケースや、公正証書遺言を希望される方には、専門家からのアドバイスも可能です。ぜひ活用してみてください。
画面の見やすさにこだわり、操作も簡単なWEBサイトです。行政書士として高齢者の相談に乗ってきたノウハウが活きています。 ぜひお試しください。