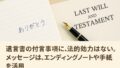不動産の相続 は、他の財産に比べてトラブルが発生しやすいという特徴があります。遺言書がなければ、相続人同士の話し合いが必要となり、場合によっては争族(そうぞく)と呼ばれる深刻な対立を生む原因にもなります。この記事では、 不動産相続 における遺言書の重要性について解説します。
なぜ 不動産相続 は揉めやすいのか?
不動産は現金のように簡単に分割できるものではありません。1つの土地や建物を相続人で等分に分けることは物理的に難しく、「誰が住むか」「誰が管理するか」「売却するかどうか」などを巡って意見が分かれやすくなります。
また、固定資産税や維持費の負担、老朽化による将来的な修繕費など、相続後に発生する義務やコストについても、意見が対立する要因になります。
遺言書を作成しておくことのメリット
遺言書があると、被相続人(亡くなった方)の意思に基づいて相続手続きを進めることができ、相続人間の話し合いを最小限に抑えることができます。特に以下のようなメリットがあります:
- 相続分が明確になる:誰にどの不動産を相続させるのかが指定されていると、無用な争いを避けられます。
- 共有相続を回避できる:遺言で単独相続を指定すれば、複数人での共有状態による管理の煩雑さやトラブルを防げます。
- スムーズな名義変更が可能:遺言書があれば、必要な手続きが簡略化されることがあります。
公正証書遺言の活用がおすすめ
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が代表的ですが、法的な有効性や手続きの確実性を考えると、公正証書遺言の作成がおすすめです。公証役場で作成されるため、偽造や紛失のリスクが低く、家庭裁判所の検認も不要です。
公正証書遺言は費用がかかるからと、尻込みされる方もいらっしゃいますが、まもるべき不動産の価値を考えたら、大した金額ではありません。
参考:日本公証人連合会
不動産相続 で、無用な争いを避けるためにできること
不動産の相続は人生の中でも大きな問題のひとつです。事前に遺言書を準備することで、家族の未来に無用なトラブルを残すことなく、円満な相続が可能になります。早めに遺言書の作成を検討してみましょう。
不動産相続 における注意点
自宅(居住用不動産)
住み続けるか売却するかで方針が分かれるため、遺言で意思を明記しておくとトラブル回避につながります。
配偶者が居住を継続できるようにしたい場合は、「配偶者居住権」の活用も検討しましょう。
賃貸物件(アパート・マンションなど)
家賃収入を誰が得るのか、管理・修繕の責任は誰が持つのか明確にしておく必要があります。
収益物件は「不動産取得」と「事業の承継」がセットになることもあるため、より慎重な設計が求められます。
空き地・山林
一見資産のようでも、管理・草刈り・税金など、手間ばかりかかる“負動産”になるケースもあります。
処分方針(売却、寄付など)も含めて考えておきましょう。
相続税にも要注意
不動産を相続すると、一定の評価額を超える場合に相続税の課税対象になります。以下の点に注意しましょう。
不動産は「路線価」や「倍率方式」で評価されるため、実際の市場価格と差が出ることがあります。
相続税の納税は原則現金一括払いのため、不動産だけを相続すると納税資金が足りなくなるケースもあります。
遺言で資産の分け方を工夫すれば、相続税負担の軽減や納税資金の確保にもつながります。
不動産は大切な財産である一方、相続をきっかけに家族間で争いを生む火種にもなりかねません。遺言書を作成しておくことで、遺された家族が円満に、かつ迅速に相続を進めることが可能になります。
「まだ早い」と思わずに、人生の節目や不動産の取得時などをきっかけに、一度、遺言書作成を検討してみてはいかがでしょうか?
不動産相続 で、遺言書がなかったためトラブルになったケース
「うちは仲の良い家族だから大丈夫!」そんな風に思っていても、遺言書がない相続は想像以上に揉めやすいものです。特に不動産は分割が難しく、感情や生活にも関わるため、相続トラブルの“火種”になりがちです。
ここでは、実際にあったトラブル事例を紹介しながら、遺言書の重要性についてお伝えします。
ケース1:実家を巡る兄弟の対立
登場人物
長男:同居していた
次男・三男:独立し別の場所に居住
状況
父が亡くなり、遺言書なし。主な財産は実家の土地と建物(評価額3,000万円)。
トラブル内容
長男は「同居して介護もしてきたから、実家は自分が相続すべき」と主張。
一方で、次男・三男は「法定相続分(3人で等分)に基づいて、自分たちにも権利がある」と反論。
不動産の単独相続か、売却・分割かを巡って激しく対立し、最終的には家庭裁判所での調停に発展してしまいました。
ポイント
遺言書があれば、「実家は長男に相続」「代償金は○○万円」など、意思を明確にすることが可能でした。争いを避け、スムーズな手続きが可能だったケースです。
ケース2:空き地を巡る相続放棄と名義問題
登場人物
相続人:3人の子ども
被相続人:母(夫は既に他界)
状況
地方にある空き地を含む数件の不動産を相続。空き地は利用価値が低く、固定資産税のみが発生していた。
トラブル内容
相続人の1人が「不要だから相続放棄する」と表明。
しかし、正式な手続きをしなかったため、固定資産税の通知が全員に届く。
誰が管理するかも決まっておらず、草刈りや近隣からのクレームに悩まされる事態に。
ポイント
遺言で「空き地は長女に相続(希望しないなら売却)」「管理に関する方針」などが書かれていれば、スムーズに処理できたケース。
ケース3:賃貸アパートの収益を巡って兄妹げんか
登場人物
長男:父と一緒に賃貸経営をしていた
長女:遠方に住む
状況
父が賃貸アパートを所有。遺言書はなし。相続人は2人。
トラブル内容
父が亡くなった後、長男がそのまま賃貸経営を継続。
しかし長女が「家賃収入の半分は自分にも権利がある」と主張し、結局は訴訟へ発展。
最終的には不動産の共有解消と代償金の支払いで和解しました。
ポイント
遺言で「アパートは長男に相続」「長女には現金で○○万円を与える」と記載されていれば、法的にも感情的にも争いを避けられたケースです。
遺言書がないと起こりうるリスク
財産の分配方針が不明で、話し合いがまとまらない
法定相続による共有状態で、管理や処分が困難に
仲の良かった兄弟姉妹が絶縁状態になることも
裁判や調停に発展すると、時間も費用もかかる
たった1枚の遺言書で、家族の未来を守れる
遺言書がないだけで、家族がバラバラになってしまう…。これは決して珍しいことではありません。不動産を所有している方こそ、早めに遺言書の作成を検討するべきです。
法的効力をしっかり持たせるには、公正証書遺言の作成がおすすめです。専門家の力を借りて、「遺す人の想い」と「遺される人の未来」の両方を守っていきましょう。
「遺言書があってよかった!」 不動産相続 で、トラブルを回避できたケース
ご紹介したように、不動産相続は「争族(そうぞく)」の温床になりやすいと言われています。しかし、遺言書がきちんと用意されていれば、相続人同士の対立を未然に防ぐことができます。ここからは、実際に遺言書があったことでスムーズに相続が進んだ3つのケースをご紹介します。
ケース1:自宅を巡る相続、兄弟円満で解決
登場人物
母(被相続人)
長男(同居していた)
次男(遠方に居住)
状況
母の主な財産は自宅(土地・建物)。遺言書がなければ、法定相続により長男と次男が半分ずつ相続する可能性がありました。
遺言の内容
「自宅は長男に相続させる。その代わりに、長男は次男に代償金として300万円を支払う。」
結果
母の死後、長男が単独で自宅を相続。代償金もすぐに用意され、次男はそれを受け取り納得。兄弟の関係も悪化することなく、スムーズな名義変更・生活の継続ができました。
ポイント
遺言書によって「相続の方向性」と「不公平感の緩和」が両立された好例です。
ケース2:賃貸物件をめぐる分配トラブルを回避
登場人物
父(被相続人)
妻(配偶者)
長女・長男
状況
父は複数の賃貸アパートを所有。家賃収入があり、資産価値も高い。不動産をどう分けるかで将来的に揉めるリスクがありました。
遺言の内容
「賃貸アパートAは長男、アパートBは長女、現預金は妻に相続させる。相続税の支払いは各自で行う。」
結果
不動産の共有を避けられたことで、名義変更や税金の申告が非常にスムーズに。
配偶者にもきちんと現金が行き渡り、生活に不安が出ることもありませんでした。
ポイント
共有による管理トラブルを回避しつつ、各相続人にバランスよく財産を分配した好事例。
ケース3:空き家問題も遺言で円満に解決
登場人物
祖母(被相続人)
孫2人(相続人)
状況
祖母が所有していた古い空き家。地元に住む孫Aと、東京に住む孫Bが相続人。
空き家は老朽化が進んでおり、管理・売却が必要な状態。
遺言の内容
「空き家は地元に住む孫Aに相続させる。不要であれば売却してよい。Bには預貯金から100万円を相続させる。」
結果
孫Aが遺言に従って空き家を相続し、すぐに売却を実行。管理や維持費の分担を巡る争いは一切起きず、孫Bも金銭を受け取って納得。
ポイント
遺言で「意思表示」と「負担の明確化」がされていたため、誰も困らずに済んだケース。
遺言書がもたらす3つの効果
①相続方針の明確化
誰が何を相続するか」をはっきりさせることで、話し合いが不要に。
②感情的な対立を防ぐ
遺言は被相続人の「最終意思」として尊重されるため、感情面の納得が得やすい。
③手続きの迅速化
不動産の名義変更、税務処理がスムーズに進行。
遺言書は“家族への最後の思いやり”
不動産が絡む相続は、たとえ少額でも争いに発展するリスクがあります。しかし、遺言書があるだけで、相続人たちの心と手続きの両面が守られるのです。
家族がバラバラにならないように、そして財産を円満に引き継いでもらうために。
ぜひ、専門家の助けを借りながら、遺言書の作成を検討してみてください。
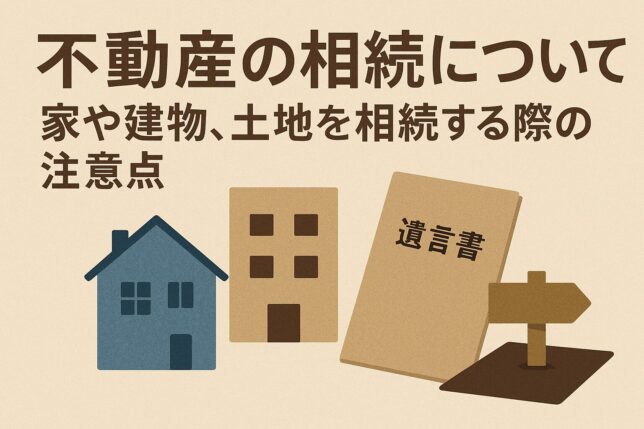
遺言書作成 もAIの時代
不動産相続の際の、遺言書作成の重要性についてご理解いただけましたでしょうか。
それでも、法律専門家に相談するのは料金がかかると二の足を踏む方もいらっしゃるかもしれません。DX(デジタルトランスフォーメーション)を標榜する岡高志行政書士事務所では、AIを活用した遺言書作成の自動作成サイトを運営しております。その名も
「遺言書AI」を利用すれば、簡単な入力で遺言書を作成できます。
人生100年時代、遺言書の作成は、より良く生きるための必須事項ともいえます。そのため、社会貢献の一環として、お客様の利用は無料としております。
公正証書をご希望の方には、公証役場と調整する部分だけを有償サービスで提供しております。
複雑なケースや、公正証書遺言を希望される方には、専門家からのアドバイスも可能です。ぜひ活用してみてください。
画面の見やすさにこだわり、操作も簡単なWEBサイトです。行政書士として高齢者の相談に乗ってきたノウハウが活きています。 ぜひお試しください。