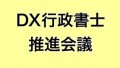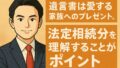人生は何が起こるかわかりません。健康で元気に過ごしているときは、まだまだ先のことと思いがちですが、万が一の備えとして「遺言書」を作成しておくことは非常に重要です。本記事では、遺言書を早めに準備するメリットやポイントについてお伝えします。加えて、遺言書を準備する際に知っておきたい、 自筆証書遺言 と 公正証書遺言 の違いについても解説していきます。ぜひ参考にしてください。
遺言書を書くメリット3つ
① 自分の意思を明確にできる
遺言書がない場合、財産の分配は法律に基づいて行われます。しかし、自分が希望する形で財産を分配したい場合は、遺言書を作成することで、その意思を明確に伝えることができます。
② 相続トラブルを防ぐ
遺産をめぐるトラブルは決して珍しくありません。家族間の争いを防ぐためにも、遺言書で分配方法を明確にしておくことが大切です。
③ 財産管理がスムーズに行える
遺言書があることで、相続人はスムーズに手続きを進めることができます。特に、不動産や金融資産などが関係する場合、手続きの負担を減らすことができます。
遺言書を作成する際のポイント3つ
① 法的に有効な形式で作成する
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などの種類があります。特に、公正証書遺言は公証人が関与するため、法的な効力が高く安心です。
② 定期的に内容を見直す
人生の状況は変化します。ライフステージの変化に応じて、遺言書の内容を定期的に見直すことが大切です。
③ 専門家に相談する
遺言書を作成する際に心配なことがあれば、専門家に相談することをおすすめします。法的なトラブルを避けるためにも、専門家のアドバイスを受けることは重要です。
このように、元気なうちに遺言書を準備することで、自分の意思をしっかりと反映させ、家族の負担を軽減することができます。万が一のことを考え、今からでも遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか?
自筆証書遺言 と 公正証書遺言 の違いとは?
実際に遺言書を作成する際に、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらを選ぶべきか悩む方も多いのではないでしょうか。このふたつには、それぞれメリット・デメリットがあり、ご自身に合った方法を選ぶことが重要です。以下に、それぞれの違いについて解説します。
自筆証書遺言 とは
① 特徴
自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きで作成する遺言書です。最近の法改正により、一部(財産目録など)をパソコンで作成することも可能になりましたが、基本的には自筆が求められます。
② メリット
- 費用がかからない(紙とペンがあれば作成可能)
- 自分の好きなタイミングで作成・変更できる
- 内容を誰にも知られずに作成できる
③ デメリット
- 法的要件を満たさないと無効になる可能性がある
- 紛失や改ざんのリスクがある
- 検認(家庭裁判所での手続き)が必要で、相続手続きに時間がかかる
公正証書遺言 とは
① 特徴
公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。証人2名の立会いのもとで作成されます。
② メリット
- 公証人が作成するため、法的に無効になるリスクがほぼない
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
- 検認が不要で、相続手続きがスムーズに進む
③ デメリット
- 費用がかかる(公証役場での手数料が必要)
- 証人2名が必要で、内容が第三者に知られる可能性がある
- 作成・変更に手間がかかる
参考:日本公証人連合会
自筆証書遺言 と 公正証書遺言 どちらを選ぶべきか?
自筆証書遺言が向いている人
- 費用をかけずに手軽に作成したい
- 内容を他人に知られたくない
- こまめに内容を変更したい
公正証書遺言が向いている人
- 法的に確実な遺言書を作成したい
- 遺言内容に複雑な財産分与が含まれる
- 相続手続きをスムーズに進めたい
このように、自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれにメリット・デメリットがあります。自身の状況や希望に応じて適切な方法を選び、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
相続がトラブルに発展するケース
相続では、思わぬトラブルが発生することも少なくありません。事前にトラブルの事例を知っておくことで、対策を講じることができます。ここでは、相続に関するよくあるトラブルをご紹介します。
遺産の分配をめぐる争い
遺産の分け方が不公平と感じる
遺産の分配が公平でないと感じた相続人が、不満を抱えて争いになるケースは多いものです。特に、特定の相続人に多くの財産が遺された場合、他の相続人が納得できないことがあります。
法定相続分と異なる遺言内容
法定相続分と異なる遺言が残されていると、相続人の間で対立が生じる可能性があります。
財産の所在が不明
隠し財産の存在
被相続人が生前に管理していた財産の一部が相続人に知らされていないことがあります。そのため、相続が発生した後で財産が発見されると、相続人間での再分配の問題が生じることがあります。
借金や負債の発覚
相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金や負債も含まれます。相続後に多額の負債が発覚し、トラブルになるケースも少なくありません。
遺言書の有効性に関する問題
遺言書が見つからない
被相続人が遺言書を作成していても、その所在が分からないと遺言の内容を実行することができません。
遺言書の形式不備
自筆証書遺言などは、法律で定められた要件を満たしていないと無効になる可能性があります。署名や押印の不備、日付の記載漏れなどが挙げられます。
代襲相続による混乱
相続人がすでに亡くなっている場合、その子供(孫)が代わりに相続する「代襲相続」が発生します。これにより、相続関係が複雑になり、トラブルにつながることがあります。
上記のような相続トラブルは、事前の準備や適切な対応によって防ぐことが可能です。遺言書の作成や財産の整理を早めに行うことで、争いを防ぐことができます。
相続について不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
不安解消! 公正証書遺言 を作成した方たちのエピソード
遺言書を作成することで、家族の将来に対する不安を解消し、安心感を得られることがあります。ここからは、実際に遺言書を作成して良かったという方の体験談を紹介します。
妻のために、相続対策をしたAさん(70代・男性)
Aさんは長年連れ添った妻と二人暮らし。夫婦には子供がいないため、自分が亡くなった後の妻の生活を心配していました。そのような中、知人の勧めで遺言書を作成することを決意しました。
「自分が先に逝ったら、妻が安心して生活できるようにと考え、公正証書遺言を作成しました。専門家に相談しながら作成したので、法的に問題なく、しっかりとした遺言書を残すことができました。これで妻に負担をかけることもないと、安心できました」
兄弟間の争いを防ぐことができた Bさん(60代・女性)
Bさんは、実家の土地や預貯金をめぐって兄弟で意見が分かれる可能性を心配していました。
「母が亡くなる前に、遺言書を作成してもらいました。そのおかげで、兄弟で大きなトラブルになることなく、母の意思に沿った形で相続手続きを進めることができました。遺言書がなかったら、今ごろ兄弟間で揉めていたかもしれません…」
事業承継がスムーズに進んだ Cさん(50代・男性)
Cさんは家業を継いでいる二代目社長。父親が高齢になり、事業承継の問題が浮上していました。会社をスムーズに引き継ぐために、父親と話し合い、遺言書を作成することにしました。
「父は昨年亡くなりましたが、しっかりと遺言書を作成してくれたおかげで、会社の相続手続きもスムーズに進みました。社員たちも安心して仕事ができ、混乱が起こらなかったのは本当にありがたかったです」
このように、遺言書を作成することで、家族間の争いや将来の不安を未然に防ぐことができます。遺言書は、財産を適切に分配するだけでなく、残された家族の安心にもつながります。
「自分にはまだ早い」と思う方もいるかもしれませんが、いつ何が起こるかわかりません。大切な人を守るために、早めに準備しておくことをおすすめします。

遺言書作成 もAIの時代
遺言書作成の重要性につきご理解いただけましたでしょうか。
それでも、法律専門家に相談するのは料金がかかると二の足を踏む方もいらっしゃるかもしれません。DX(デジタルトランスフォーメーション)を標榜する岡高志行政書士事務所では、AIを活用した遺言書作成の自動作成サイトを運営しております。その名も
「遺言書AI」を利用すれば、簡単な入力で遺言書を作成できます。
遺言書AIは、ガイダンスに沿って相続人・資産情報などを入力することで、遺言書が無料で作成できるWEBサイトです。 正式な遺言書は 自筆証書遺言 としてご自身で手書きする。もしくは 公正証書遺言 として公証人に作成していただくこととなります。
遺言書作成の部分は自動化されていますので、一度開発してしまえば運営コストはかかりません。そのため、お客様の利用は無料としております。
公正証書とするために、公証役場と調整する部分だけを有償サービスで提供しております。
複雑なケースや、公正証書遺言を希望される方には、専門家からのアドバイスも可能です。ぜひ活用してみてください。
UIのわかりやすさにこだわったシンプルなWEBサイトです。行政書士として高齢者の相談に乗ってきたノウハウが活きています。 ぜひお試しください。