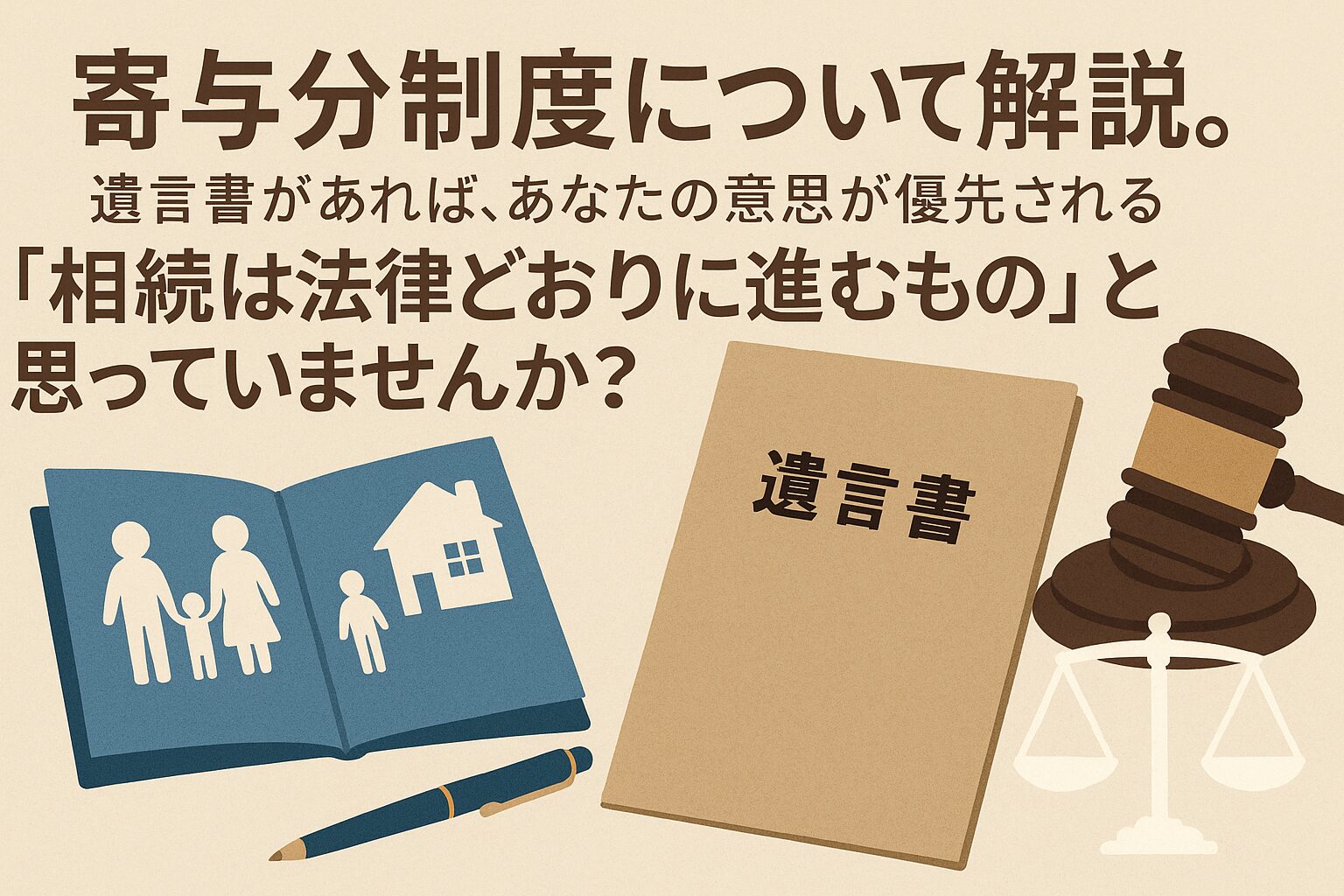「相続は法律どおりに進むもの」と思っていませんか?
実は、相続には法律(民法)のルール=法定相続分がありますが、遺言書がある場合はその内容が原則として優先されます。この記事では、遺言書が相続に与える影響、法定相続との違い、遺留分や 寄与分制度 について解説します。
遺言書は“法定相続”よりも強い効力を持つ
民法では、遺産を相続人にどのように分けるかを「法定相続分」として定めています。たとえば、配偶者と子どもが相続人であれば、それぞれ1/2ずつの割合になります。
しかし、遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割を行うのが原則です。
例えば…
- 法定相続:妻が1/2、長男が1/4、長女が1/4
- 遺言書がある場合:「すべての財産を妻に相続させる」と記載 → 妻が全てを相続できる
つまり、故人の「意思」が法定のルールよりも優先されるというのが基本です。
遺言書を作成する際、遺留分には注意が必要
しかし、どれだけ遺言書が優先されるといっても、すべて自由にできるわけではありません。
法定相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれる、最低限の取り分が保障されています。
遺留分とは?
- 配偶者・子ども・直系尊属(親など)には、法定相続分の半分の遺留分があります。
- たとえば、「全財産を第三者に相続させる」という遺言書があった場合でも、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という法的手続きを通じて金銭の請求ができます。
遺留分がない人もいる
- 兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、遺言書で「兄には何も相続させない」と書くことも可能です。
遺言書があることで得られるメリット
①相続トラブルの回避
被相続人(亡くなった方)の意思が明確になるため、相続人同士の対立が起こりにくくなります。
②財産の分け方を自由に設計できる
介護してくれた子どもに多く相続させる、事業を継ぐ子に事業用資産を相続させる、など柔軟な対応が可能です。
③手続きがスムーズ
相続人全員の同意が不要なケースもあり、不動産登記や預金の払い戻しが円滑に進みます。
遺言書の種類
遺言書には主に次の2種類があります。
| 種類 | 特徴 | 注意点 |
| 自筆証書遺言 | 自分で書ける。費用がかからない。 | 法的な形式不備で無効になることも |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成。確実で安全。 | 作成に費用と手間がかかる |
不動産や相続トラブルを避けたい方には、法的な不備が少ない「公正証書遺言」の作成を強くおすすめします。
参考:日本公証人連合会
相続を「あなたの意思」で決めるなら、遺言書が不可欠
相続の場面で一番大切なのは、遺された家族がもめずに安心して次の一歩を踏み出せること。
そのためには、あなたの「想い」をきちんと伝える手段として、遺言書が最も有効です。
相続を法律任せにせず、あなた自身の言葉で残す準備をはじめましょう。
ぜひ、信頼できる専門家と相談しながら、早めの遺言書作成をご検討ください。
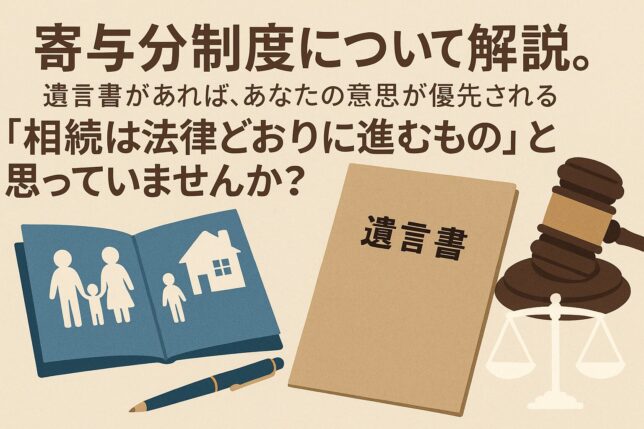
遺産分割の 寄与分制度 について解説
相続が発生した際、遺言書がなければ、「誰がどれだけの財産を相続するか」という問題は非常にデリケートです。その中で、「寄与分(きよぶん)」という制度は、特定の相続人が他の相続人より多く遺産を受け取る可能性があるルールです。ここからは、「寄与分制度」について、わかりやすく解説します。
寄与分制度 とは?
寄与分制度は、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対して、その貢献度に応じて相続分を加算する制度です。これは民法第904条の2に基づく制度で、相続人間の公平を図る目的で設けられています。
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
民法 第904条の2
寄与分が認められる具体的なケース
寄与分が認められるためには、「特別の寄与」があったことが必要です。以下のようなケースが該当します:
- 介護などの療養看護:長年、無償で親の介護をしてきた子ども。
- 事業への貢献:家業を継ぎ、利益を出して被相続人の財産を増やした相続人。
- 金銭的援助:住宅の購入や生活費の補助など、実質的な経済支援を行った場合。
重要なのは、「通常期待される家族の扶助義務の範囲を超えているか」が判断基準になることです。
寄与分の主張方法と手続き
寄与分は自動的に認められるわけではありません。次のようなステップが必要です。
- 話し合い(協議):他の相続人と遺産分割協議の中で寄与分を主張します。
- 調停または審判:協議で合意に至らない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。この中で寄与分も審理されます。
- 証拠の提出:どれだけ貢献したかを証明する書類(介護記録、金銭の送金記録など)を用意することが大切です。
寄与分が認められた場合の影響
寄与分が認められると、相続人全体の遺産からまず寄与分を差し引き、その後残りの財産を法定相続分に応じて分割します。
例:
被相続人の財産:3000万円
子Aが特別な介護で寄与分500万円と認められた
残り2500万円を他の相続人と法定分割
寄与分制度 注意点
寄与分を主張するには根拠と証拠が必要です。
相続人間の争いの火種になることもあるため、冷静な対応が重要です。
相続人でない人(例:息子の妻など)は、2019年の法改正により「特別寄与料」として請求できるようになりました。
寄与分制度は、被相続人に対して特別な貢献をした相続人の努力を正当に評価する仕組みです。しかし、主張するには手続きと証拠が必要であり、他の相続人とのバランスにも配慮が求められます。
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人を除く。「特別寄与者」)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
民法 第1050条
遺産分割で寄与分を主張してトラブルに発展したケース
相続の場面でよく起こるトラブルのひとつが、「寄与分(きよぶん)」の主張を巡る対立です。
寄与分は認められるかどうかの判断が難しく、他の相続人との間で感情的な対立を生むことも少なくありません。
ここからは、実際に寄与分の主張がきっかけで相続トラブルに発展したケースをご紹介しながら、注意点と対策を解説します。
長男が寄与分を主張して兄妹間の関係が悪化
登場人物
- 被相続人:父(自営業で不動産を所有)
- 長男:父の事業を手伝っていた
- 長女・次女:独立して他県に在住
状況
父が亡くなり、遺産としては自宅と賃貸アパート、預貯金が数百万円。
遺言書はなかったため、3人の子どもが法定相続人となり、原則として均等に分けることになるはずでした。
しかし、長男が「自分は父の事業を何年も手伝ってきた。その間、報酬も受け取っていない。だから寄与分として他の兄妹より多く相続すべきだ」と主張。
一方、長女と次女は「それは家業を継いだ立場で当然のこと。特別な貢献ではない」と反論。
感情的な対立がエスカレートし、遺産分割協議は決裂。最終的に家庭裁判所の調停に持ち込まれる事態となりました。
トラブルに発展しやすい寄与分制度
寄与分は、民法に規定された正当な制度ですが、実際の相続の場面では次のような問題が起こりがちです。
「貢献」の認識が相続人ごとに違う
当事者は「十分に貢献した」と思っていても、他の相続人にはその実感がない場合が多いものです。
証拠が不十分
「同居していた」「介護をしていた」「家業を手伝った」といった内容は、口頭での主張だけでは証明しづらく、調停や審判でも認められにくいことがあります。
感情的な対立を生む
「自分の方が苦労した」「恩知らずだ」といった感情がぶつかり、兄弟姉妹の関係に大きな亀裂が入ることもあります。
このケースの結末
家庭裁判所の調停では、長男が主張する寄与分の額と、他の兄妹が納得できる額に大きな差があり、最終的には審判に移行。
結果として、長男の主張の一部が認められたものの、当初希望していた金額には届かず。
さらに、相続手続きには2年以上かかり、関係修復も困難な状態となってしまいました。
対策1:遺言書で「貢献」を明文化しておく
このような争いを避けるには、被相続人自身が生前に「誰にどのくらい相続させるか」を明確にしておくことが一番有効です。
たとえば、遺言書で以下のように記載できます。
「長男○○は、私の生前に家業を支えてくれたため、不動産の8割を相続させる。長女・次女には預貯金の各半分を相続させる。」
このような記述があれば、相続人同士で寄与分を巡る主張の必要がなくなります。
対策2:生前贈与や報酬で調整しておく
家業の手伝いや介護など、貢献が明らかな場合は、生前に報酬や贈与で感謝の意を示しておくのも有効です。
そうすることで、相続時に「寄与分」として調整する必要がなくなり、トラブル回避につながります。
相続トラブルを防ぐには、遺言書作成が有効
寄与分の主張は正当なものであっても、証明が難しく、他の相続人の感情を逆なですることも多いため、慎重に扱う必要があります。
一番の予防策は、遺言書の作成ともいえます。
家族がもめないための「最後のメッセージ」として、あなたの意思をしっかり残しておきましょう。
遺言書作成 もAIの時代
遺言書作成の重要性につきご理解いただけましたでしょうか。
それでも、法律専門家に相談するのは料金がかかると二の足を踏む方もいらっしゃるかもしれません。DX(デジタルトランスフォーメーション)を標榜する岡高志行政書士事務所では、AIを活用した遺言書作成の自動作成サイトを運営しております。その名も
「遺言書AI」を利用すれば、簡単な入力で遺言書を作成できます。
人生100年時代、遺言書の作成は、より良く生きるための必須事項ともいえます。そのため、社会貢献の一環として、お客様の利用は無料としております。
公正証書をご希望の方には、公証役場と調整する部分だけを有償サービスで提供しております。
複雑なケースや、公正証書遺言を希望される方には、専門家からのアドバイスも可能です。ぜひ活用してみてください。
画面の見やすさにこだわり、操作も簡単なWEBサイトです。行政書士として高齢者の相談に乗ってきたノウハウが活きています。 ぜひお試しください。