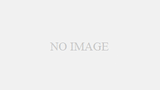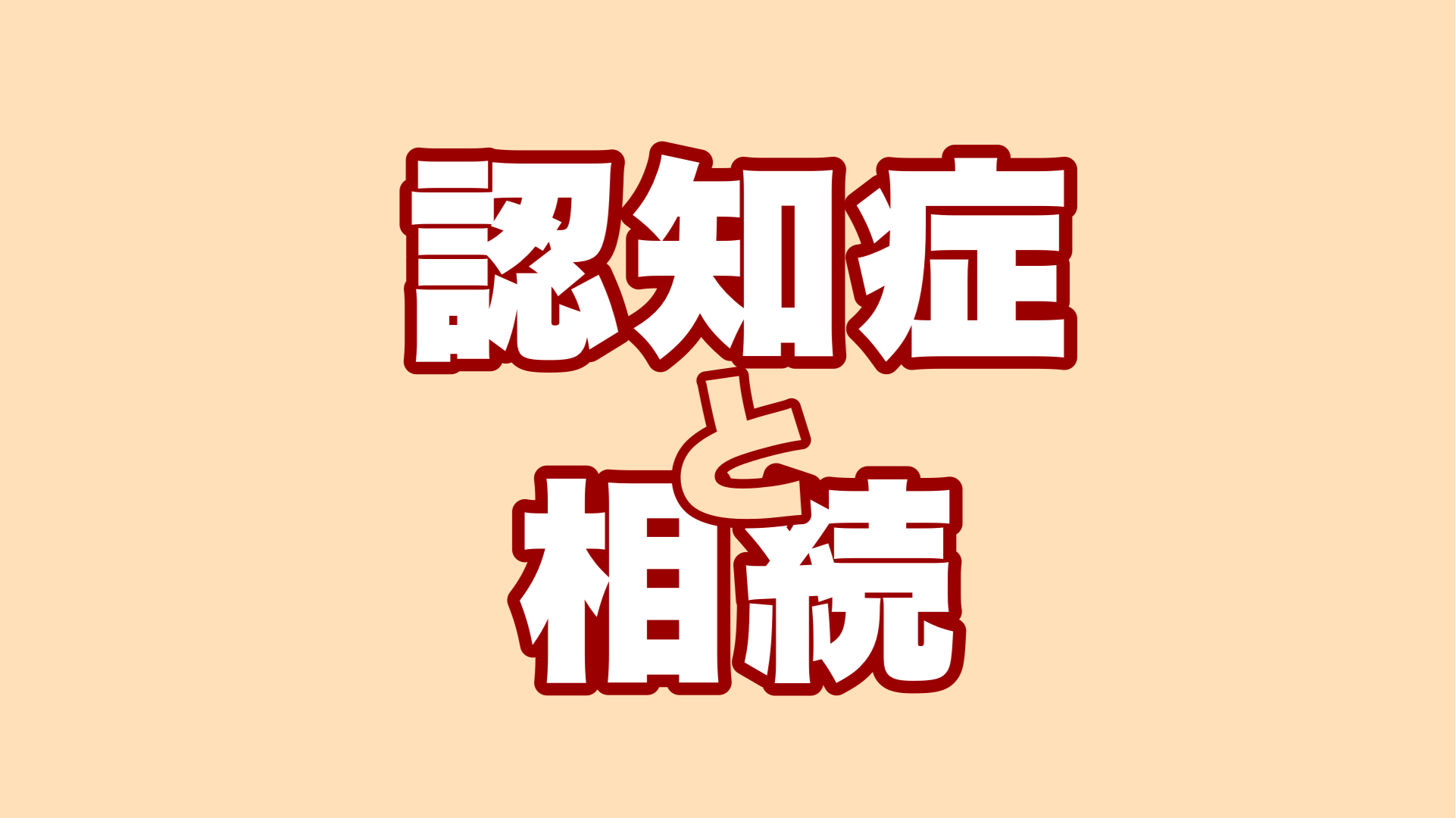遺産分割を行う上でまず大前提となるのは
「遺言書があるのか」
遺言書が見つかれば 遺言書の意思に従って遺産分割を行い、
遺言書が見つからない 場合には法定相続人で話し合いを行うこととなります。
今回は遺産分割を行う際に遺言書が発見されない場合の対処法をかんたん解説いたします。
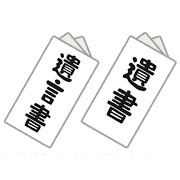
1.遺言書を見つける
遺言書の有無や保管先を生前に確認できている状態が一番良いのですが、そう簡単にいかない場合の方が多いかと思います。遺産分割を行うには遺言書を見つける必要があります。
まず遺言書の種類を知り、それぞれの保管先を徹底的に確認することが重要です。
遺言書は大きく自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つに分かれます。
自筆証書遺言は役場などを利用せずに自ら書いた遺言書です。そのためほとんどの場合が自宅保管になるため、まずはこの自筆証書遺言がないか家の隅々まで相続人同士で協力し合いながら探しましょう。
自筆証書遺言でも、法務局保管している可能性もあります。法務省からの通知を待つ、もしくは、確認を行ってみましょう。
自筆証書遺言が見つからなければ、公正証書遺言または秘密証書遺言として公証役場に保管されている可能性があります。
せっかく故人が用意された遺言書が発見されないと、遺産分割が協議事項となってしまい争族のタネになります。相続手続において遺言書を調査・検索することがまず大切です。
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合
保管場所がわからず、遺言通りに相続されない可能性があります。
上述の法律改正によって、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになりました。
公正証書遺言の場合1989年以降、公正証書遺言の作成年月日を、公証人連合会でデータベース化しています。どこの公証人役場でも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、被相続人の遺言の有無を照会することができます。
遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場に対してすることができます。
申出の際の必要書類は、①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、③申出人の本人確認の書類です。
なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています。
詳細:日本公証人連合会
また自筆証書遺言と秘密証書遺言は公証人による内容確認などが行われていないため、内容に不備などがあれば家庭裁判所の判断により無効となる可能性があります。
遺言書が見つかったとしても、遺言書はなかったものとして今後の遺産分割が進んでしまうため注意が必要です。
2. 遺言書が見つからない 場合の遺産分割
自宅や遺言者の身の周り、公証役場を探しても遺言書が見つからない場合には遺言書はないものとして遺産分割を行うこととなります。
遺産分割協議を行うために、まずは法定相続人を遺言者の戸籍をもとに確定します。
この戸籍を辿る作業を怠ると、万が一隠し子など今まで存在を把握していなかった法定相続人が後から現れた場合に遺産分割を再協議する必要が出てきます。
法定相続人の確定については慎重に行いましょう。
法定相続人の確定の際に法定相続人が亡くなっている場合でも代襲相続が発生する場合があるため注意が必要です。
法定相続人の確定と並行して、相続財産と債務を把握することも重要となります。
債務が相続財産を上回る場合には相続放棄をすることが可能ですが、これには相続人になったことを認知してから3ヶ月という期限が設けられています。遺産分割協議をスムーズに行うためにも相続財産をリスト化することが大切です。
相続財産と法定相続人が確定すれば、遺産分割協議で法定相続人全員の合意の得られる分配を決めていきます。
この協議において全員の合意が得られれば、遺留分などについては考慮せずに1人が全財産を受け取る形でも問題ありません。
法定相続人全員の合意がなければならないため、遠方の方は電話やリモートで参加をする必要があります。
戸籍から法定相続人を把握できたものの、疎遠や音信不通で遺産分割協議に取り合ってもらえない場合には、利害関係のない人から不在者財産管理人を選出します。家庭裁判所に権限外行為の許可申請を行うことで、法定相続人の代わりとして遺産分割協議に参加することが可能となります。
遺言書が発見されない場合は遺産分割協議によって分配を決めるしかありません。
財産に関わるシビアな内容を、話し合いで全員の合意が得られる状態にまとめ上げることは容易ではありません。
少しでも揉め事になるようなことがあれば法の力を借りるのも1つの手段と言えるでしょう。
遺言書をこれから用意するという場合にはこのような複雑な問題を抱えないよう、公正証書遺言を残しておくことをおすすめします。